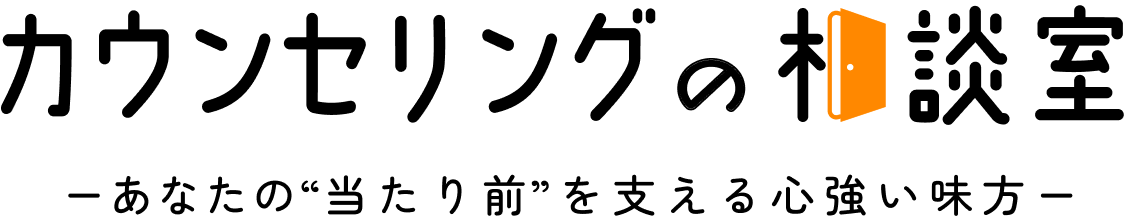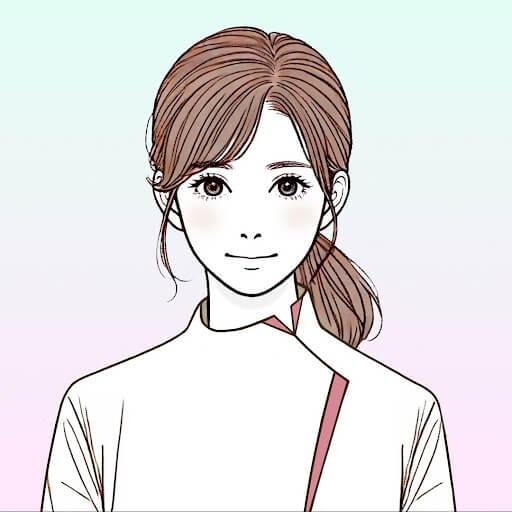「栄養カウンセリングと栄養指導は何が違うんだろう?」
「やることにも違いがあるのかな…」
栄養カウンセラーや管理栄養士などへの興味から、栄養カウンセリングと栄養指導の違いが気になる方は多いですよね。
言葉の意味は理解できても実際の仕事ではどんなことをするのか、どんな職業に必要なのかなどがイメージできない方もいるはず。
そこで本記事では栄養カウンセリングと栄養指導の違いをわかりやすく解説します。この記事を読めば、それぞれの特徴や違いが明確になりますよ。
- 栄養カウンセリングは相手に気づきと変化を促す
- 栄養指導は健康に必要な食事や栄養の知識を伝える
- 健康増進を支えるには栄養カウンセリングのスキルは欠かせない
本記事を音声で聴く
栄養カウンセリング・栄養指導とは?
栄養カウンセリングと栄養指導は、どちらも栄養や食生活を改善するアプローチ手法の1つです。なぜなら、栄養カウンセリングと栄養指導は、健康や栄養面の不安を抱えている人におこなわれるためです。
どちらも似ているように感じられますが、目的やアプローチの仕方が異なります。
| 栄養カウンセリング | 栄養指導 | |
|---|---|---|
| 目的 | 本人の改善する力を引き出す | 正しい食事の知識や方法を理解・実践させる |
| アプローチ | 対話を通じて気づきや行動の変容を促す | 教育的に知識や情報を伝える |
| 方法 | 傾聴質問共感動機づけ面接など | パンフレットやプランの提供指導や講義 |
| 対象者のかかわり | 自主性を重視するため能動的 | 指導者が主体になるため受動的 |
| 必要な心理面への配慮 | 食事にまつわるストレスや自己肯定感などを考慮する | 重視していない |
栄養カウンセリングは相手の心理や行動に寄り添い、気づきと変化を促すかかわり方です。一方、栄養指導は、健康に必要な食事や栄養などの「知識を伝える」教育的アプローチです。
栄養カウンセラーの仕事内容や年収などを詳しく知りたい方は下の記事を参考にしてください。

医療現場では併用するケースが多い
栄養カウンセリングと栄養指導は、医療現場で併用するケースが多くあります。両者を必要とする人は、食事がかかわる健康や疾病上の理由を抱えているためです。
栄養に関する知識を伝えるだけでは、行動の継続や変化が難しい場合があります。そのため初回では「栄養指導」、継続的には「栄養カウンセリング」で習慣化を支える必要があるのです。
たとえば、間食や過食で悩む人の栄養カウンセリングと栄養指導では、下記のように対応が異なります。
| 栄養カウンセリング | 継続面談で習慣化を支援する(動機づけ) 体重が減らない理由を一緒に探る(行動分析) 不安や失敗に直面する相手の心理面に寄り添う(傾聴) |
| 栄養指導 | 初回面談で食事の基本を説明(教育) 食品交換表の使い方を伝える指導(知識の提供) 食生活の改善を評価する(フィードバック) |
栄養カウンセリングと栄養指導の両輪で、相手の健康的な食事を支えます。
栄養カウンセラーに不可欠なスキル
栄養カウンセリングと栄養指導は、どちらも栄養カウンセラーに不可欠なスキルです。なぜなら知識の提供や不適切な食習慣への指摘は、少なからず相手にプレッシャーを与えてしまうためです。
相手が変化を望んでいない場合もあり、一方的な指導では十分な効果を引き出せない恐れがあります。相手がカウンセラーと会うことや話すことを苦痛に感じるようになると、改善は見込めません。
栄養カウンセラーには、知識だけでなく相手に寄り添う姿勢が求められます。
栄養カウンセラーになるための具体的な手順を知りたい人は、下の記事を参考にしてください。

栄養カウンセリングと栄養指導の違い
ここからは次のトピック別に、栄養カウンセリングと栄養指導の違いを解説します。
実施目的
| 栄養カウンセリング | ・相手の心理面や生活習慣を踏まえ、自発的な行動の変化を促す ・長期的な継続や主体的な行動を支援する |
| 栄養指導 | ・健康や疾患に応じて正しい食事や栄養の情報を提供する ・短期的で具体的な改善を目指し教育的にかかわる |
栄養カウンセリングは、相手の内面に寄り添い気づきと変化を与えることが目的です。一方、栄養指導では知識を伝え、具体的な改善へ導くことが目的です。
栄養カウンセリングと栄養指導は、期間やアプローチのポイントが異なります。
主な方法・技法
| 主な方法・技法 | |
|---|---|
| 栄養カウンセリング | ラポール形成(信頼関係の構築) 動機づけ面接(習慣化の促進) ABC分析(行動に気づく) 3つのS(自己理解を深める) SMARTゴール設定(達成可能な目標の提示) 自己効力感の向上を支援(ポジティブフィードバック) |
| 栄養指導 | 食事や生活の調査・聞き取り (全体像の把握) 食事の栄養計算・過不足の評価(質や量を評価) 食品交換表や献立の解説(代替できる案を提案) 栄養の目安量の説明(情報の提供) 改善度の確認(共通認識の再確認) 再評価(指導・観察の継続) |
栄養カウンセリングでは相手の心理や行動、栄養指導では正しい知識の提供や教育を重視します。栄養カウンセリングではすぐに結果が出なくても否定せず、行動したことを賞賛します。一方、栄養指導では具体的な改善策を示し、実践を促す方針です。
相手が変化を望んでいなければ、どのように支援をしたとしても、十分な結果は得られません。栄養支援の効果を得るには、カウンセラーのかかわり以外に対象者の姿勢が大きく影響します。
対象者の姿勢
| 対象者の姿勢 | |
|---|---|
| 栄養カウンセリング | 方法がわからないうまくいかず悩んでいるサポートが行動のきっかけになる受動的 |
| 栄養指導 | 明確な目的がある教わったことを行動に移せる主体的 |
栄養カウンセリングと栄養指導の効果を左右するのが、対象者の姿勢です。対象者の向き合い方や受け止め方で、同じ支援でも得られる効果が異なります。
栄養カウンセリングが必要なのは、相反する感情に悩んでいる方です。一方、栄養指導が必要なのは主体的に行動でき、短期の改善が見込める方です。
栄養カウンセリングと栄養指導、どちらも対象者の姿勢で支援の効果が変わります。そのため、支援者には相手の状態を見極め、適切なかかわり方を選ぶことが求められます。
まとめ
本記事では、栄養カウンセリングと栄養指導の共通点や違いについて解説しました。どちらも健康や栄養に関する支援ですが、アプローチやかかわり方は異なります。
気づきや行動の変化に寄り添い、長期的にサポートするのが栄養カウンセリングです。一方、知識の提供や短期的な改善を目的とするのが栄養指導です。
両者の視点や技法を持っていると、相手の悩みに的確に応じ、より健康的な生活へ導きやすくなるでしょう。